|
解説
【幾つかの事柄】
【参考資料一覧】
【謝辞】
|
新城島からの帰島後、【幾つかの事柄】について調べて見ました。
また、【参考資料一覧】と【謝辞】を掲載いたします。
【幾つかの事柄】
旅から帰ってきた後、私の中で幾つかの事柄が疑問符付きで残りました。
1.八重山の海にジュゴンはいつまでいたのか
2.ジュゴンの肉は首里王府に納められていたのか、またジュゴンを食べていたのはどのような人々だったのか
これを埋める為に、蔵書の一次資料(当時書かれた文献、公文書)をあたったところ、
「与世山親方八重山島規模帳」(西暦1768年 和暦 明和5年)
「富川親方八重山島諸締帳」 (西暦1875年 和暦 明治8年)
の二つの資料から「海馬」(ジュゴン)に関する記述が見つけました。
両資料とも首里王府から八重山・宮古の派遣された「検使」(行政監察官)である与世山親方、富川親方が八重山・宮古の行政状況をつぶさに調査し王府へ報告すると共にその問題点を指摘・指導するという内容です。「検使」である両名は「親方」(ウェーカタ)という上級官吏であり、その資料の性格から考えて、当時の八重山の状況を公正かつ正確に表しているといってよいでしょう。
資料中の原文は漢語候文で、現代語の対訳もついているのですがそれでも分かりずらいので私が一部口語体に直して記述します。
「与世山親方八重山島規模帳」の記述
『新城村は諸役人からジュゴンならびにカメなどをいつも所望され、村の悩みとなっているので、今後は御用(首里王府へ納める事)以外に所望する事を禁止する』
わずかこれだけですが、首里王府への納税としてジュゴンを捕獲する以外に、「諸役人」つまり八重山の地方役人達が勝手に新城島の人々にジュゴンを納める事を命じて捕獲させていたという事実が浮かびあがってきます。
首里王府、地方役人達、さまざまな人々がジュゴンを欲していた事がうかがえます。
|
 |
「富川親方八重山島諸締帳」の記述は二つあります。
『御用物(首里王府への納税品)のジュゴンは新城村に限って捕獲指示書を出しており、その他の者から欲しいという要求があっても渡さないという事になっているのにもかかわらず守られていない。
御用物から余分が出てもその他の者の要求に応えて渡してしまっているので、年々、ジュゴンを捕らえるのに多人数で日数を要するようになり、困っているというのは問題である。今後は法に定めたように、その他の者の欲しいという要求には応えない事。
また、余分となったジュゴンは在番・頭が印をして保管させて後日の御用に使うように取り締まる事』
文中は御用以外の要求とあり、具体的に誰が「その他の者」なのかは書かれていませんが、前掲の「与世山親方八重山島規模帳」の内容から見れば、これもまた「諸役人」と見るのが妥当でしょう。
つまり、1768年から1875年までの約100年間、相変わらず地方役人達の職権濫用による私的な捕獲指示と御用物の不正取得が行われていたという事になります。
これも八重山の海からジュゴンが消えた原因の一端であろうと思われます。
事実、このおかげで捕獲に「多数の人数と日数」が必要になるほどに頭数が少なくなっている事。一時的に捕獲余剰となったジュゴンも「在番」(首里王府からの八重山派遣駐在官)「頭」(“間切”という行政区の長)という八重山行政機関の中でも最高位にあたる者が厳格に保管・管理しなくては納税に応えられないという事実が読み取れます。
|
 |
このジュゴン捕獲に関する苦労はもうひとつの文からもうかがえます。
『首里王府に納めるジュゴンの調達は、新城村に受け持ちを命じてある。ところが年々、それを捕らえるのに多くの人足が必要となり困っている。
捕獲に必要な人足数を定めた法規を変えて人足の数を増やそうとしたが、この人足数はかつて定められているので、いまさら王府御用とはいえ規定を変えることは難しい。
一応、島で一斤につき四名ずつ増やし、地方役所の指示による労役の人足から差し引くようにするので、そのように心得る事』
(注.この「一斤につき四名」という記述が不明でした。重さを示す一斤(約600グラム)の事なのか、それとも他の意なのか、文脈を鑑みてつじつまの合う言葉が見つかりませんでした。)
この記述からは、最優先でジュゴンを捕獲しなくてはならない「御用」にすら多数の人数と時間が必要となっている事が読み取れます。
「富川親方八重山島諸締帳」(諸事全般の規定指示集)は明治8年に発行されています(首里王府の行政権停止と沖縄県知事の任命(一連の琉球処分措置)はこの後の明治12年・西暦1879年)。
本編の老人の口碑(言い伝え、伝説)では「明治の前にはいなくなった」との事ですが、「明治に始めにはまだジュゴンはいたが、姿見かけることはほとんどなく、その捕獲には大変な労力が必要だった」というのが正確なところでしょう。
ちなみに老人の口碑の「王府には肉は納めていなかった」ですが、首里王府への米や上布の納付要領などを事細かに定めた「富川親方八重山島諸村公事帳」(公務に特化した規定集)に「ジュゴン」に関する記述がなかった事(見落としているかも知れませんが)を書き添えておきます。
まだ、幾つか疑問符が残る事柄はありますが、ここから先の扉を開けるのは一旅行者の手ではなく学究者の方の手になるものだと思いますので、私の書籍の上での「ざん」を追う行為もここまでとします。
|
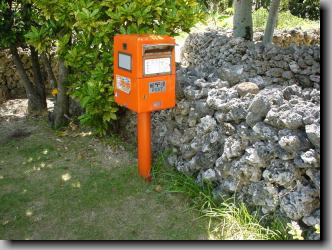 |
【参考資料一覧】
著作権法を鑑み物語を構成するにあたって使用した書籍とHPの一覧を掲載します。
HPは公共性の高いもの(水族館、新聞社)のみ使用しました。
※物語の端緒
・「もの食う人びと」 辺見庸著 (角川文庫刊 1997年)
・「八重山の人頭税」 大浜信賢著 (三一書房刊 1971年)
※ジュゴンについて
・「鳥羽水族館」のHPより。
鳥羽水族館機関紙2001年秋号【No.39】。「人魚学入門(2)北限のジュゴン奄美から沖縄へ」
※ステラー海牛について
・「幻の動物たち(上巻)」 J=J=バルロワ (ハヤカワ文庫刊 1990年)
※北太平洋の毛皮狩猟者について
・「ロシアについて 北方の原型」司馬遼太郎著 (文春文庫 1998年)
※新城島・沖縄史について
・「島嶼社会の変化と生活圏編成に関する研究」 (財団法人沖縄地域科学研究所刊 1978年)
・「八重山の明和大津波」 牧野 清著 (私家発行 1981年)
・「八重山ジャンルごと小事典 」崎原恒新著 (ボーダーインク社 1999年)
・「南島地域史研究」 南島地域史研究会(文献出版 1984年)
・「八重山手帳 2002年」 (南山社刊 2002年)
・「角川日本地名大事典 47 沖縄県」 (角川書房刊)
・「沖縄大百科事典」 (沖縄タイムス社刊)
・「やえやま GUIDE BOOK」 (南山社刊 2001年)
・「高等学校 琉球・沖縄史」 (沖縄県歴史教育研究会刊 1995年)
・「沖縄タイムス社」のHPより。
「島を往く・船人くらし(8) 新城島(竹富町)<1999年12月18日 朝刊16・17面>」
※ジュゴンに関する第一次資料
・「石垣市史叢書1 富川親方八重山島諸締帳」 (石垣市役所総務部市史編集室)
・「石垣市史叢書2 与世山親方八重山島規模帳」 (石垣市役所総務部市史編集室)
・「石垣市史叢書3 富川親方八重山島諸村公事帳」(石垣市役所総務部市史編集室)
|
 |
【謝辞】
新城島への傭船の手配等にお手数を御掛けし、
また私の我侭な「ざん」を追う行動に御同行くださったSさんとその同伴者の方に心より感謝いたします。
ありがとうございました。
|
  |